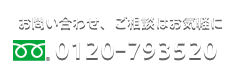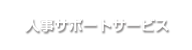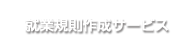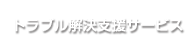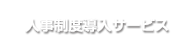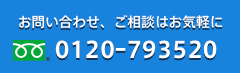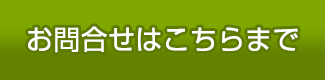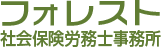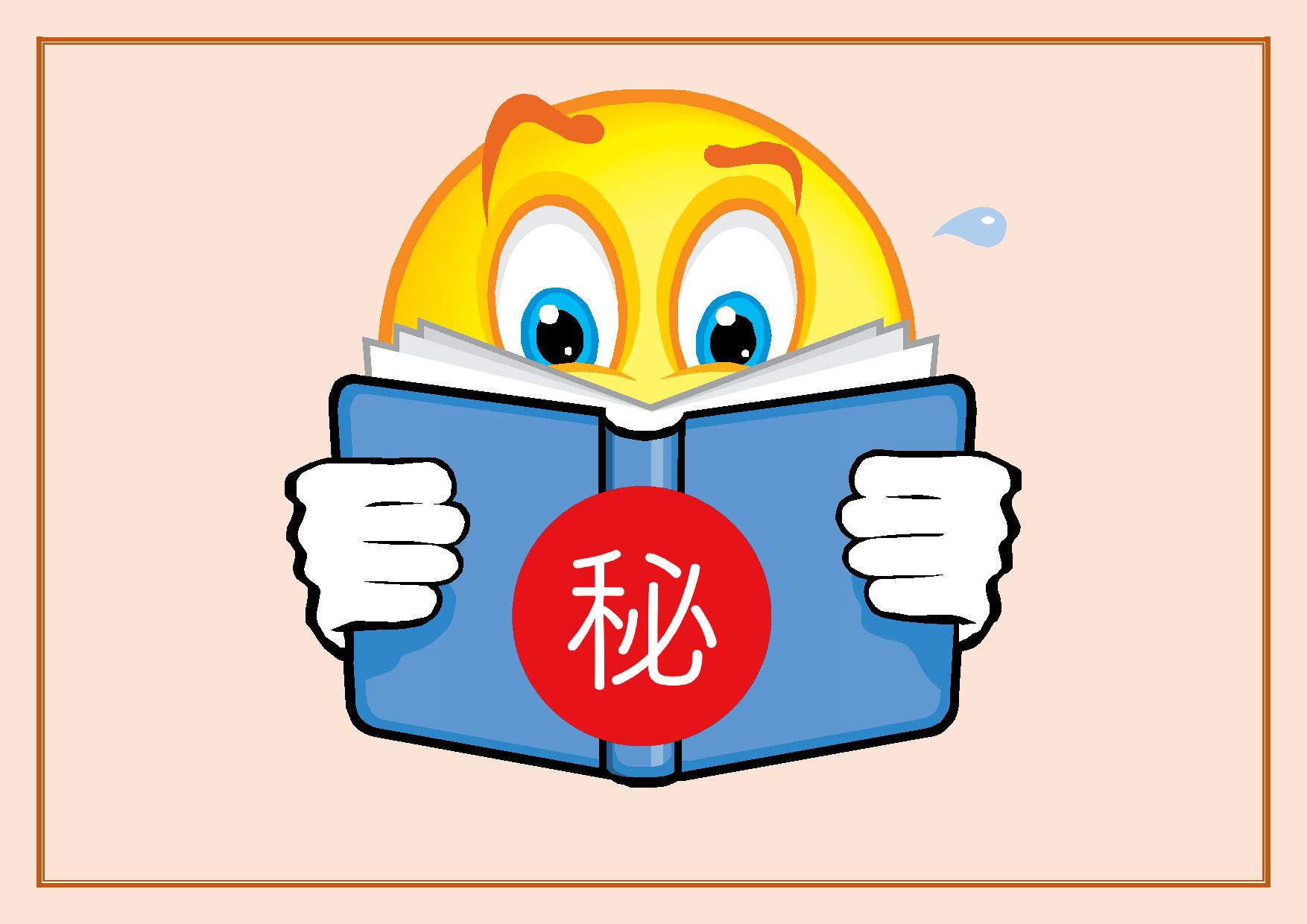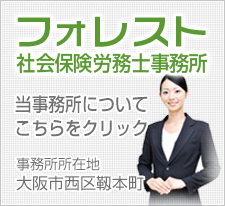厚生労働省はテレワークのガイドラインを改定し、新たなテレワークのガイドラインを公表しました。
―――テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(厚生労働省)―――
|
今回の改定では、このガイドラインが、テレワークの推進を図るためのものであることを明示する観点から、そのタイトルを、次のように改めました。
改定前 「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
改定後 「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
そのうえで、次のような内容が盛り込まれました。
●テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要があること。
●テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等は、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえないこと。
●テレワークを行うことによって生じる費用負担については、個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、その状況は様々であるため、労使のどちらが負担するか等についてはあらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましいこと。
●テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましいこと。 など
●また、テレワークにおける労働時間の把握については、「パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業及び終業の時刻を確認すること」のほか、「労働者の自己申告により把握すること」も考えられるとしています。
|
☆ 厚生労働省では、使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくことができるよう、このガイドラインの周知を図っていくこととしています。
既にテレワークを導入されている場合や、テレワークの導入を検討されている場合には、確認しておきたい内容です。詳細につきましては、気軽にお尋ねください。
令和3年4月から労災保険の「特別加入」の対象を拡大
労災保険法の施行規則の改正により、令和3年4月から、次のように、特別加入制度の対象を拡大することとされました。
―――――令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました――――
|
【前提】労災保険の特別加入制度
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認める制度です。
特別加入できる方の範囲は、中小事業主等(第1種特別加入)、一人親方等・特定作業従事者(第2種特別加入)、海外派遣者(第3種特別加入)に大別されます。
<今回追加されたもの> ●一人親方等の特別加入の対象に追加 ・柔道整復師 ・創業支援等措置に基づき事業を行う方
●特定作業従事者の特別加入の対象に追加 ・芸能関係作業従事者 ・アニメーション制作作業従事者
<保険料は?> これらの方は、いずれも第2種特別加入をすることになり、これらの方の第2種特別加入保険料率は、労働保険徴収法の施行規則において、いずれも「1,000分の3」とされました。
|
☆ 対象となる方におかれましては、気軽にお声掛けください。詳細を説明させていただきます。
なお、「創業支援等措置に基づき事業を行う方」とは、改正高年齢者雇用安定法による65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置のうちの「創業支援等措置」として、委託契約等に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に係る委託契約等に基づいて高年齢者が行う事業を、労働者を使用しないで行う方やその事業に従事される労働者以外の方をいいます。
「創業支援等措置」は、雇用以外の措置であるため労災保険の適用がないところ、特別加入は認めようという趣旨で設けられたものです。